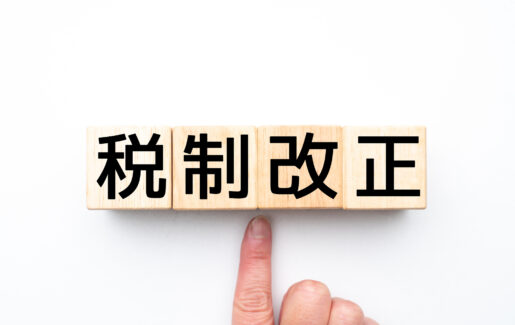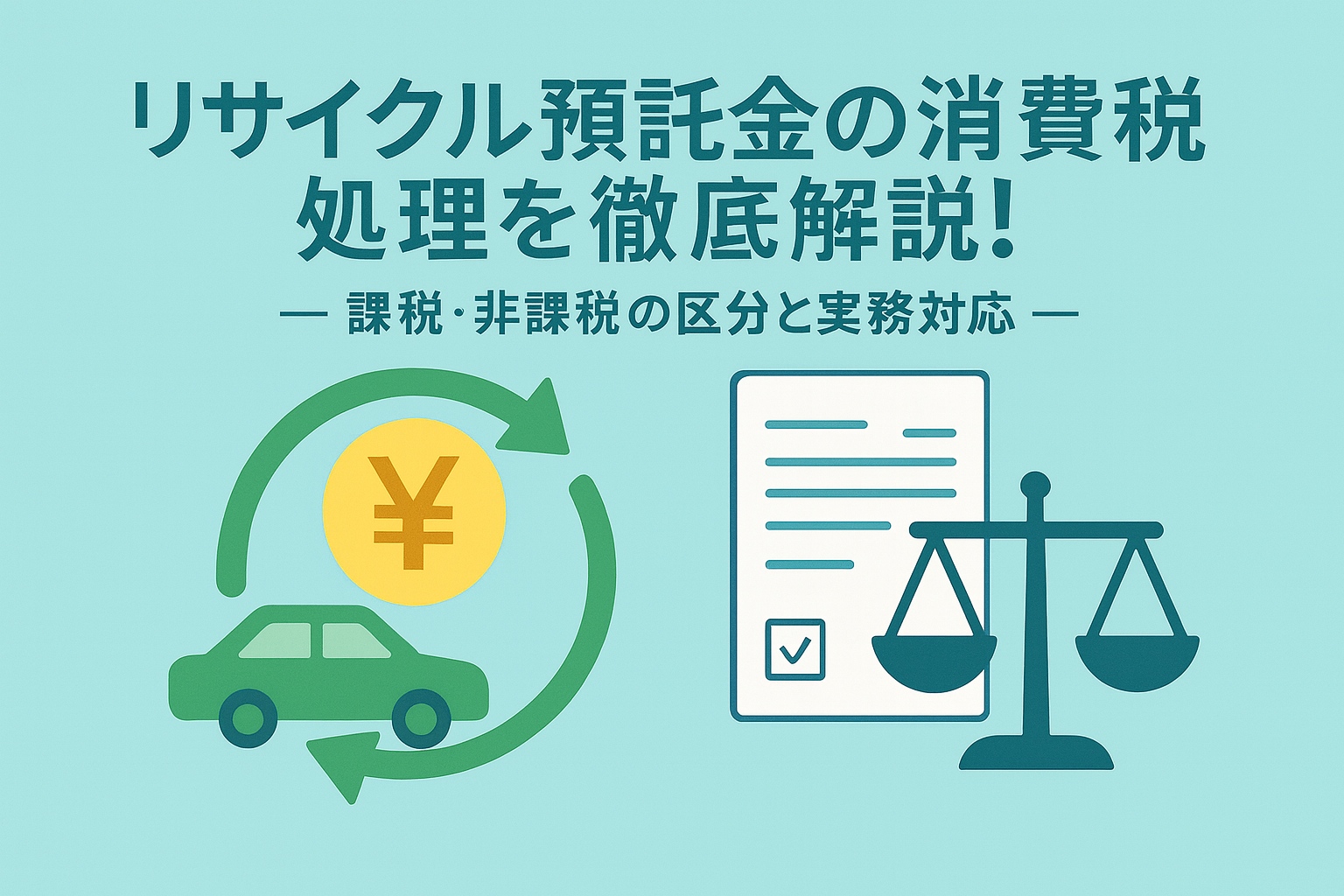みなさんは、生成AIを使っていますか?
この数年で急速に進化を遂げている生成AI。
もはや生成AIはこれからのビジネスにおいて競争優位性を高めるために必要不可欠な存在であり、中小企業においても積極的な活用が求められています。
しかし、業務効率化やアイデア創出に役立つ一方で、そこには情報漏えい・契約違反などのリスクも潜んでいます。
本記事では、ビジネスシーンにおいて生成AIを活用する際に押さえておくべきリスクと注意点について、わかりやすく解説します。
生成AIとは?
ChatGPTなどの生成AIは、インターネット上に存在する膨大な情報量の学習データをもとに文章や画像を自動生成することができるツールです。アイデア出しや課題解決など、企業にとっても様々な場面で有用な存在ですが、その利用プランには有料版と無料版があり、また、個人向けプランと法人向けプランが存在しています。ビジネスにおける生成AI利用にあたっては、これらのプラン選択、入力する情報の取扱い、生成されたデータの取扱いの3つのポイントについて注意する必要があります。
- プラン選択:法人向けの有料プランを推奨
- 入力する情報の取扱い:機密情報や個人情報の取扱いは要注意。匿名化処理必須。
- 生成物の取扱い:画像等の生成物は著作権侵害等の恐れあり。
AI利用に潜むリスク
生成AIに情報を入力する行為は、体系的には外部企業のサーバーに情報を提供している行為と同じです。ゆえに、その情報が機密情報や個人情報などに該当する場合、情報漏えいとして様々な法的リスクが伴ってきます。
また、生成された画像などのデータが、第三者の著作権を侵害する恐れもあるため、生成物の取扱いについても慎重な注意が必要となってきます。
Tips情報漏えいリスク:入力した顧客情報が外部に流出する可能性。
法的リスク:著作権侵害や秘密保持義務違反。
信用リスク:誤情報の発信による企業の信頼失墜。
出典:総務省「AI利活用ガイドライン」・中小企業庁「中小企業のデジタル活用事例集」
実務において注意点すべき重要なこと
1.プラン選択が重要
ビジネス利用における生成AIサービスは、法人向け有料プランを推奨します。
主要な生成AIサービスでは、多くの場合、法人向け有料プランにおいてユーザーとAI企業との利用契約に秘密保持契約(NDA)とデータ処理契約(DPA)が盛り込まれており、オプトアウト設定もデフォルトで組み込まれているため、情報管理と責任所在が明確になっています。これに対して、個人向けプランや無料プランでは、入力データをAIの学習に利用されない設定(オプトアウト設定)こそできたとしても、そこにNDAやDPAといった正式な取り決めが存在しないため、AI企業側が責任を負わない契約体系となっています。この論点は、個人情報保護法における「第三者提供」にあたるか否かの判断においても重要な要素の一つとされています。
POINT☛ Microsoft Copilot、ChatGPT、Google Geminiなどは比較的安全
☛ 法人向けプランであっても、中国製AIのDeepSeekなどは、オプトアウト設定ができず、NDA、DPAも不透明のため要注意
2.入力する情報の取扱いが重要 ~匿名化でリスクを減らす~
機密情報や個人情報などの重要な情報は、絶対に入力しないでください。
個人名・住所・企業名などを含むデータは直接入力せず、必ず匿名化・加工して投稿することを徹底してください。
また、匿名化処理等を施したとしても、できるだけ相手先から生成AIへの情報利用について同意を得ることが望ましいとされています。
3.生成物の取扱いが重要 ~著作権侵害リスク~
生成AIが生成したイラスト等の画像データには、2つの著作権の問題があります。
1つは生成物そのものの著作権が誰に帰属するか、という点で、もう1つがその生成物が第三者の著作権を侵害するものか、という点です。
例えばChatGPTではその利用規約等において生成物の著作権がユーザーに帰属することを明記しているため、前者のリスクは解消できますが、その生成物に某有名キャラクターが描かれている場合など、第三者の著作権を侵害しうる可能性は十分に考えられます。
生成した時点では問題ありませんが、それを自社の広告やホームページ、SNSなどで利用した場合、商用利用として損害賠償の問題が起こり得るため、くれぐれも注意してください。
4.運用ルールやマニュアル等の策定が重要
企業等の組織としての運用にあたっては、社内ルール等をきちんと定めることを推奨します。
まずは上記のリスクや注意点を理解した上で、デジタル庁や総務省が策定しているガイドラインを参考に、自社に合ったルールやマニュアルを整備しましょう。
まとめ
生成AIは非常に手軽に使えるツールで、ビジネスの可能性を広げる一方、リスクを正しく理解しなければ大きなトラブルに発展しかねません。
リスクをきちんと理解した上で、適切な利用を心掛けましょう。
※本記事は、掲載日時点における法令等に基づいて作成しております。