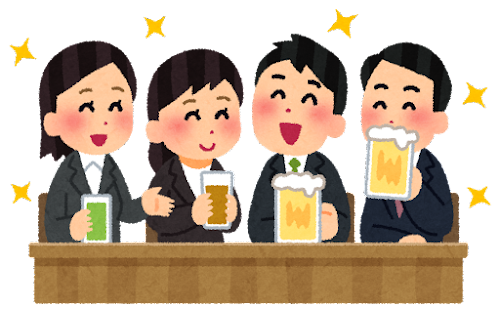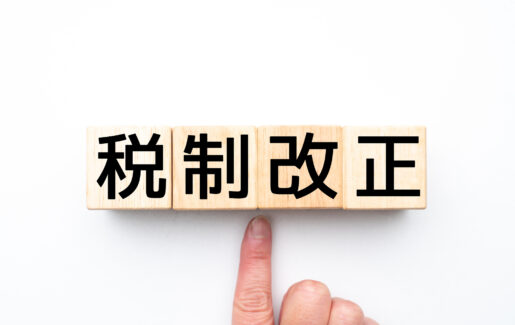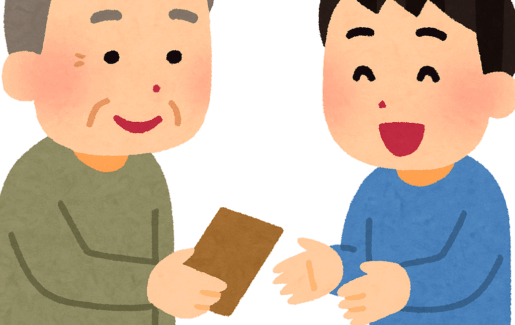令和7年度 住宅ローン控除改正 ― 若者・子育て世帯に追い風!
〜借入限度額の上乗せと床面積緩和の最新ポイント〜
1.住宅ローン控除とは?そして令和7年の改正の方向性
マイホーム購入時に税負担を軽くできる「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」は、多くの家庭が利用する人気の税制優遇制度です。令和7年度の税制改正では、急激な住宅価格の上昇や金利上昇の影響を踏まえ、特に子育て世帯や若年夫婦世帯を支援する方向で見直しが行われました。
今回の改正は、大きな構造変更ではなく、現行制度をベースにした延長と重点化が特徴です。つまり、「これから住宅を取得する若年層・子育て世帯」にとって、非常に追い風となる内容です。
2.改正の主なポイント(概要)
✅ ① 子育て世帯・若年夫婦世帯への借入限度額の上乗せ
現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、子育て世帯等について、住宅ローン控除における借入限度額について上乗せを行う。
※「子育て世帯等」とは、①年齢40歳未満であって配偶者を有する者、②年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者、③年齢19歳未満の扶養親族を有する者。
この「上乗せ措置」により、子育て世帯や若年夫婦世帯が取得する住宅については、通常よりも高い借入限度額で控除が受けられます。たとえば、認定長期優良住宅やZEH水準の住宅を取得する場合、借入限度額が最大 5,000万円 となり、控除額の上限も広がります(控除率は従来どおり年末残高の0.7%)。
✅ ② 床面積要件の緩和 ― 40㎡以上に拡大
子育て世帯にとっての利便性の向上や、様々な世代・ライフスタイルに応じた住宅取得ニーズに対応する観点から、床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和されます(令和7年12月31日以前に建築確認を受けたものが対象)。
これにより、これまで「50㎡未満で適用外」とされていたコンパクト住宅も、所得1,000万円以下であれば控除の対象になるチャンスが広がりました。都市部の狭小地やマンション購入など、現代的な住まい方にも対応する柔軟な制度設計です。
3.制度の全体像 ― 改正前後の比較
| 項目 | 改正前(令和6年度) | 改正後(令和7年度) |
|---|---|---|
| 控除率 | 年末残高×0.7% | 変更なし |
| 控除期間 | 最大13年 | 変更なし |
| 借入限度額(子育て・若年夫婦) | 認定住宅5,000万円、ZEH水準4,500万円、省エネ住宅4,000万円 | 同上限額で令和7年も延長・適用 |
| 床面積要件 | 所得1,000万円以下で40㎡以上(令和6年末まで) | 同条件を令和7年12月31日まで延長 |
| 省エネ非適合住宅 | 一部対象 | 原則対象外に |
出典:財務省「令和7年度税制改正の概要」、国土交通省「住宅税制の改正概要」
このように、「住宅ローン控除」という制度そのものの枠組み(控除率・期間)は変わらず、対象世帯の範囲拡大と条件緩和が中心です。
4.なぜこの改正が行われたのか ― 政策の狙い
- 住宅価格高騰への対策:特に首都圏では新築価格が10年前より20〜30%上昇。若年層の取得負担を軽減する狙い。
- 子育て支援政策の一環:住宅取得は「家族形成の第一歩」とされ、少子化対策の文脈でも重要。
- 省エネ化の推進:環境配慮型住宅への誘導を強め、脱炭素社会の実現を加速。
つまり、住宅ローン控除=税制優遇でありながら、実質的には社会政策の一部としての機能を果たしています。
5.注意点 ― 制度の「期限」と「条件」を見落とさない
✅ 建築確認と入居期限
床面積緩和や借入上限の優遇を受けるには、令和7年12月31日までに建築確認を受けた住宅が対象。入居時期が遅れると制度適用外になる場合があるため、契約スケジュールの確認が重要です。
✅ 所得制限と住宅性能
合計所得金額1,000万円以下であることが条件。さらに、省エネ基準に適合しない住宅(「その他の住宅」)は、今後控除対象外となる方針。
✅ 手続き上のポイント
控除を受けるためには、初年度は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で控除を継続できますが、住宅ローン残高証明書や性能証明書の提出を忘れずに。
6.税理士が伝えたい「今やるべき3つの準備」
- 自分が「子育て世帯等」に該当するか確認 → 年齢・配偶者・扶養親族の条件をチェック。
- 建築・入居スケジュールを明確に → 建築確認の時期で制度の可否が決まる。
- 住宅性能証明を早めに取得 → 省エネ基準適合住宅であれば、控除額・期間の優遇が受けられる。
7.まとめ ― 「延長された今こそ動くタイミング」
令和7年度の住宅ローン控除改正は、若年・子育て世帯に向けた支援強化が大きな柱です。住宅価格の高騰が続く中で、「上乗せ」「緩和」「省エネ」という3つの視点から制度が再構築されました。
「いつか買いたい」ではなく、「今動く」ことで最大限の控除メリットが得られるのが今回の特徴です。制度の期限(令和7年12月31日)を意識して、早めの検討をおすすめします。