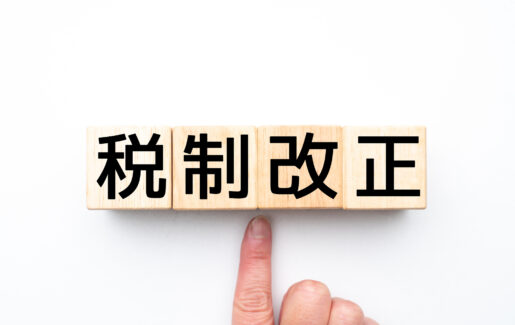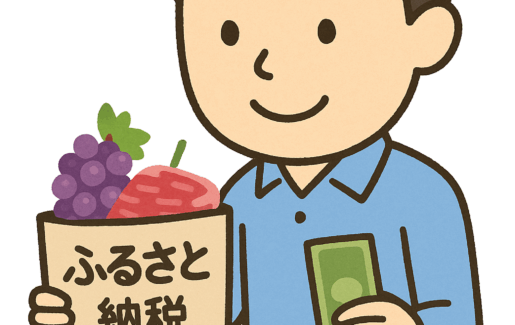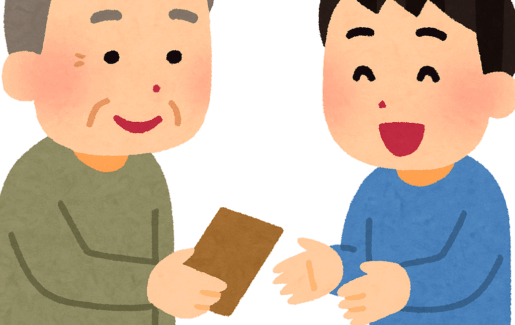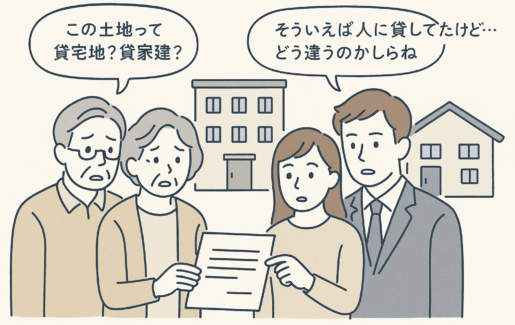年末調整で迷わない!経理担当者向け
特定親族特別控除の適用条件と実務におけるポイント
はじめに
2025年分から、特定親族特別控除という新しい制度が始まりました。対象は「生計を一にする19~22歳の親族」で、扶養控除の対象外でも一定の所得要件を満たせば控除の適用余地があります。この記事では、制度の全体像から年末調整での確認ポイントを整理します。
背景・概要について
制度の骨子
納税者に、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等がいて、その親族が控除対象扶養親族に該当しない場合、当該親族の合計所得金額に応じて3万~63万円(全9区分)を所得から控除できます。2025年分から適用/2025年12月1日施行です。なお、11/30以前の準確定申告は適用不可で、12/1以降は更正の請求で適用できます。
対象親族の範囲
「親族等」には配偶者は含まれませんが、里子(都道府県知事から養育委託された児童)は含みます。
年齢・所得の要件
年齢は12/31時点で19~22歳、所得は合計所得58万円超~123万円以下が対象です(※脚注)。
脚注:「給与のみ」の場合の“188万円”は、所得判定を給与収入に換算した目安値です。収入≠所得に注意。
事業専従者の要件
- 青色:その年を通じて一度も専従者給与の支給を受けていないこと(支給がなければ要件を満たし得ます)。
- 白色:白色申告者の事業専従者でないこと(該当したら不可)。
「生計を一にする」の考え方
同居は必須ではなく、生活費・学費等の継続送金などの実態により判断します。
年末調整での確認ポイント
1. 年齢要件の確認(基準日=12/31)
- その年の12月31日時点で19~22歳であることを確認します。
2. 生計同一の実態確認
- 同居かどうかではなく、生活費・学費などの継続的な送金等の事実で判断します。
- 記録(通帳・振込控等)を従業員から提示されれば、確認・メモ化しておくと差戻しを防げます。
3. 所得要件の確認
- 当該親族の合計所得金額が58万円超~123万円以下であるかを確認します。
- 給与のみのときは収入188万円以下が目安です。
- 注意:判定は収入ではなく合計所得です(収入≠所得)。
4. 事業専従者の区分確認(青色/白色で異なります)
- 青色申告者の事業専従者:その年を通じて専従者給与の支給がないこと。
- 白色申告者の事業専従者:事業専従者に該当しないこと。
5. 扶養控除との排他確認
- 当該親族が控除対象扶養親族に当たらないこと(同時適用不可)を確認します。
6. 重複適用の排他条件
- 当該特定親族本人が自分で本控除を適用していないこと。
- 他の者の申告書に当該親族が「源泉控除対象親族の特定親族」と記載され、源泉徴収なしになっていないこと。
- 従業員本人が他者の申告書で「源泉控除対象親族の特定親族」と記載され、源泉徴収なしになっていないこと。
7. 国外居住親族が関係する場合の書類対応
- 親族関係書類および送金関係書類(等)を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければなりません。
- 提示・回収のタイミングと保管先を社内ルールに落とし込みます。
8. 様式の回収・保管
- (略称)給与所得者の特定親族特別控除申告書を回収し、年末調整の証憑として保管します(※正式名称は本文末注)。
まとめ
- 要件確認は年齢・生計同一・所得・事業専従者・扶養控除との排他・重複排除の6本柱で進めます。
- 国外居住親族が関わるときは提出又は提示が義務の書類対応を失念しないよう、年調フローに組み込みます。
- 様式は略称運用でも、正式名称を社内掲示・保管ラベルに併記すると取り違えを防げます。