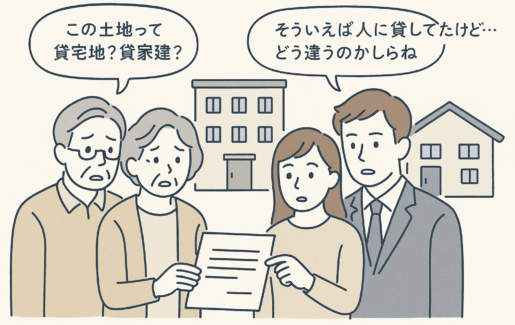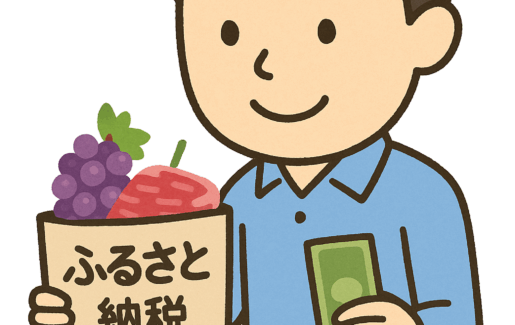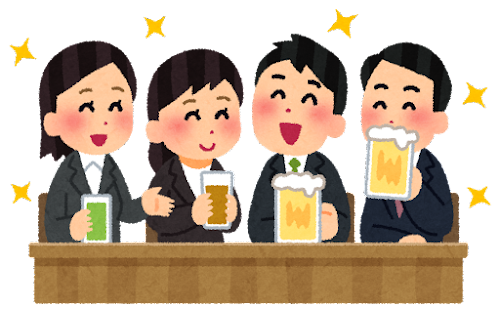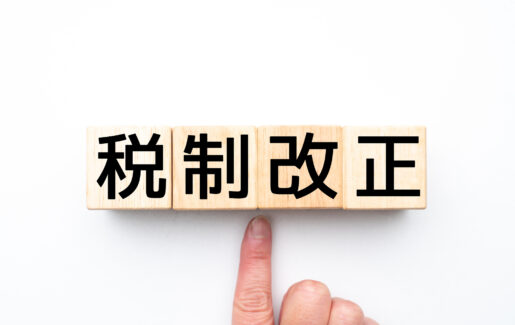はじめに
「7月と11月に届く予定納税の通知、まとまった金額の支払いが負担…」
そんなお悩みをお持ちの個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
予定納税は前年の所得をもとに計算されるため、今年の業績が下がっている場合には、資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。
また、場合によっては「支払えないのでは」と不安を感じる方も少なくありません。
本記事では、所得税及び復興特別所得税の予定納税の仕組みと資金繰りの工夫、さらに支払いが困難な場合に利用できる減額申請のポイントを、わかりやすく解説します。
所得税の予定納税とは?
予定納税とは、前年の所得税額が15万円以上の場合に、原則として翌年7月と11月に2回に分けて納税を求められる制度です(国税庁「予定納税制度」参照)。
-
対象:前年分の確定所得税額が15万円以上の方
-
納付回数:原則2回(7月・11月)
-
計算方法:前年の所得税額+復興特別所得税額の合計 × 1/3 を各期に納付
この制度は、確定申告時の負担を平準化するとともに、国の税収を安定させる目的があります。
資金繰りへの影響
予定納税は前年ベースで算定されるため、業績が落ちていても前年並みの金額を求められることがあります。資金ショートを防ぐためには、売上入金の一部を「納税用口座」に振り分けるなど、日常的な資金管理が重要です。
減額申請の提出期限と見積基準日
「今年の収入が大きく減った」「災害や病気の影響で納税が難しい」といった場合、予定納税額を減らすための減額申請が可能です。
-
第1期・第2期分の両方を減額申請する場合
提出期間:7月1日~7月15日
見積基準日:その年の 6月30日現在 の収支見込み -
第2期分のみを減額申請する場合
提出期間:11月1日~11月15日
見積基準日:その年の 10月31日現在 の収支見込み
(いずれも期限が土日祝日の場合は翌平日が期限。出典:国税庁「予定納税額の減額申請」)
復興特別所得税の取り扱い
減額申請の対象は「所得税額」に加え、「復興特別所得税(所得税額の2.1%)」も含まれます。そのため、申請の際は「所得税+復興特別所得税」の合計額をもとに見積計算を行う必要があります。
申請に必要な書類と注意点
-
申請には「予定納税額の減額申請書」を提出
-
根拠資料として収支内訳書や試算表などを添付
-
税務署による審査があり、「資金が苦しい」という理由だけでは認められない場合もある
-
e-Taxまたは紙の申請が可能
「必ず認められる」ものではなく、証拠資料に基づき合理的に説明できるかが重要です。
まとめ
予定納税は、前年の所得に基づく仕組みのため、事業環境の変化にそぐわない金額が課されることもあります。資金繰りを見越した準備が必要ですが、もし支払いが困難な状況であれば、期限内に正しく減額申請を行うことが重要です。
※本記事は、掲載日時点(2025年10月現在)における法令・公的情報に基づいて作成しております。