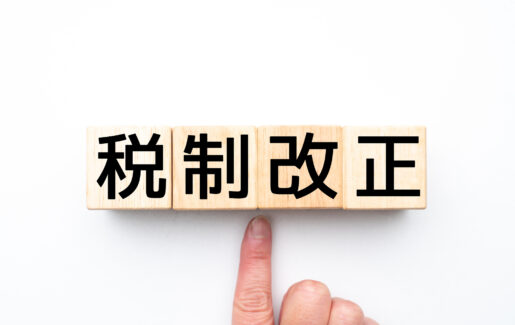はじめに ~親の「もしも」に備える~
日本人の75歳の10人に1人、85歳の3人に1人は認知機能の低下が起こるといわれております。一度認知症を発症して判断能力が低下すると、相続対策や財産管理が難しくなるため、元気なうちに公的制度を活用した対策を進めておくことが大切です。
ここでは、「遺言」「家族信託」「任意後見」の各制度についてご紹介します。
1.各制度の位置づけ
「遺言」「家族信託」「任意後見」の各制度は、それぞれどのようなことに備えるか「目的」とするところが違います。
遺 言:財産承継に備える制度
家族信託:財産管理と財産承継に備える制度
任意後見:財産管理と身上監護に備える制度
2.各制度の特徴
■遺言
生前に、親本人が財産の分け方を指定する制度です。
遺言の方法には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
①公正証書遺言:公証人と立会人を通じて公文書化する遺言手続き。
②自筆証書遺言:本人の自筆押印だけで完結する遺言手続き。
自筆遺言は法定要件を満たす記載方法等でなければなりません。
また、その記載内容の有効性は不確定です。相続人等による紛失、隠匿、改ざんのリスクもあります。
後者のリスクを回避する方法としては、法務局の遺言書保管制度の活用が有効です。
POINT☛ 公正証書遺言は公証人と立会人が必要。時間と費用もかかる。
☛ 自筆証書遺言は全て自筆で作成が必要(別紙財産目録はPC入力したものも可)。
☛ 親本人に判断能力があるうちにしか作成できない。
☛ 財産管理権限はないため、親の詐欺被害を防ぐことはできない。
■家族信託
信頼できる家族と信託契約(主に公正証書)を締結し、特定の財産の管理を任せる制度です。
賃貸不動産などの管理を任せた場合、不動産の家賃収入は親に帰属させたまま、その不動産に関する契約関係の管理を全て家族が管理することができます。また、親が認知症になったあともその権限は継続されます。
POINT☛ 特定の財産の管理権限を家族に託しておくことができる。
☛ 親本人が認知症になっても、財産管理権限は継続される。
☛ 親本人に判断能力があるうちにしか契約できない。
☛ 契約の内容次第で、範囲や権限、期間を柔軟に設計できる。
☛ 契約設計の柔軟性は高いが、複雑なため専門家の関与が重要。
■任意後見
認知症などで将来の判断能力が衰えたときのために、親が自らの意思で後見人を事前に選定しておく制度です。
法定後見の場合は裁判所が後見人を指定するため、必ずしも家族が後見人として選ばれるとは限りません。
また、法定後見は裁判所の審理等を要するため、後見登記完了までの期間が任意後見に比べて長期化します。
POINT☛ 親本人が希望する人物を後見人に指定できる。
☛ 判断能力が喪失したときの後見登記がスムーズ。
☛ 親本人に判断能力があるうちにしか設定できない。
☛ 身上監護や財産管理等に関する権限の空白期間が生じない。
3.制度の選び方のアドバイス
- 制度は似ているようで、「いつから・何のために使うか」で選び方が変わる。
- 制度選びで失敗しないためには、“何を一番重視したいか(財産承継・財産管理・介護等の身上監護)”を明確にすることがカギになる。
- 以下のような比較表を使うとわかりやすい
| 制度 | 遺言 | 家族信託 | 任意後見 |
| 主な目的 | 財産の承継 | 財産管理+財産承継 | 身上監護+財産管理 |
| 発効タイミング | 死亡後 | 契約締結後 | 判断能力喪失後 |
| メリット | 財産承継の意思を残せる | 柔軟な財産運用が可能 | 判断能力低下時に円滑な保護が可能 |
| 注意点 | 詐欺被害等は防げない | 設計が複雑 | 財産運用にかなりの制限を受ける |
4.まとめ
認知症対策は「元気なうち」が最良のタイミング!
- 親の認知症への備えは、「元気なうち」しかできない対策が多い。
- 制度の違いを理解し、必要に応じて税理士や司法書士などの専門家に相談することが大切。
- まずは「目的を明確にすること」から始めましょう。